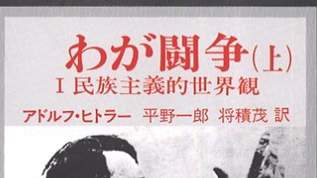【20歳の群像】第5回 中島義道

本コラムの作者ドリーさんは、村上春樹氏の「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」Amazonレビューにおいて、日本記録である23000票以上の「参考になった」を集め、大きな話題になりました。
この連載「20歳の群像」では、過去の偉人が20歳の頃に何をしていたのか?
ドリーさんならではの視点と語り口で迫ります!(いまトピ編集部)

なにを隠そう自伝マニアなのである。べつに隠してるわけじゃないが。フツーの人よりは自伝というものに多く接してきていると思う。この企画でも、もう四人の偉人をとりあげてきた。
ポールオースター、ジョブズ、三島由紀夫、プーチン、それぞれに異端で、やはり天才とはこうあるべきものだな、と感嘆させられることもあった。
しかし自伝の魅力は、本来は、こんなところに自分がいる、という共通点の発見だと思うのだ。今回、とりあげる自伝はそういう共通点という意味合いで、ほかの自伝とは一線を画しているのである。
ボクの自伝コレクションのなかでもベスト1に君臨する自伝。いろんな自伝を読んできたが、ここまで「これ、ボクですやん」と思ったことはない。
ボクが自伝に求める要素、ダメ感、挫折感、生きづらさ感、くすぶってる感、非青春感、孤独感、あらゆるエレメントをかねそなえた、まさに最強の自伝。その著者は中島義道。哲学者である。
もちろん知らない人もいるだろう。知ってる人は、おそらくめっちゃ知ってる。そんな人。
哲学者というからには、何か思想をもっているわけで、どういう思想かというと、これがものすごくシンプルで。「どうせ死んでしまうのに、なんでみんなそんな必死こいてがんばってるの?」という。こういうことをずーっと言っている哲学者なのである。この時点で、最高だが。
これまでとりあげてきた成功者には皆各自、追い求める「何か」があった。
ものを書くことであったり、美だったり、政治だったり、成功に至るプロセスにはかならず「何か」にかける熱いパッションがあり、それはどの成功者にも欠けてはならない要素だと思っていた。しかし今回のとりあげる偉人はもうそういう成功者が情熱をかける「もの」に対し、
「そういう情熱かけてつくったもん、なんの意味あんの? どうせ死んじゃうんだよ。死んだら、何もかも無だし、この地球だっていつかはほろびてチリと化しちゃうんだよ。そんなもんに情熱かけてどうすんの? ねぇどうすんの?」ってことをずーっと野次を入れる。そんな成功者なんである。
こんな成功者いていいのか。
しかしこのオヤジ、ある種の人々の心をとらえてはなさない。
ある種の人ってのは(ボクを含め)「人生を降りたがっている人々」「けっこう人生がつらくて、生きづらい人」とか、世の中で盛り上がってるもんに対して「なんかのれねーな」と思ってる人。そういう人にはまさにリスペクトされやすい世捨て人ヒーローのような存在なんである。
成功者にもアッパー系とダウナー系があって、今回のまさに、成り下がり志向のダウナー系の権化というか。
まず子供のときからもう、その虚無りかたは、人並みはずれている。子供ときにグアム島で戦士した兵士の写真を見て、そのあまりの残酷な死に方に衝撃をうけ「生きていたってしょーがないじゃん」と思っちゃうのだ。このとき小学生。もちろんこういうことを思う子供は五万といるけど、中島少年は徹底してこれを忘れない。
「あああああああああああああああ、ボク、死んじゃう・・・ボク死んじゃう・・・ボク死んじゃう・・・」
と歩きながらつぶやき、しまいには離人症みたいに、どこか別の世界へとんでっちゃうような、そんな子供で。
そんな子供だから、学校でもとけこめないのである。
「死」のことずっと考えていると、人間同士の社会的儀礼みたいなものが「できなくなってしまう」というやっかいな特質まであらわれ、どういうことかというと、たとえば先生が「さぁーみんなー今日はアリスクリームよお。食べなさーい」といって生徒の目の前にドサぁーとアイスクリームを置くでしょ、そしたら、ほかの子供らはわぁーってアイスクリームのとこにむらがるんだけど、中島少年は、ガチガチに硬直してして動けないのである。
「うわ・・・ここでアイスクリーム欲しがったほうが、子供らしいよな、絶対子供らしいよな、いったほうがええよな」って一瞬でも思うと、もう金縛り状態。挨拶なんかにしても先生に「おはよう」がいえない。
いわゆる「子供らしさ」とか「生徒らしさ」という、社会が要求する「○○らしさ」というものに対し、極度な嫌悪感を抱き始め、しかもそれに付随して運動がまったくできないので、たとえば校庭にいるときにふいにボールが飛んできて向こうから「おーい。とってくれよう」とか言われると気絶しそうになったりと(ボクですやん)、ボールがこないように「安全なところ」を必死に探し回ったりするところとか、ぼっちの習性パターン「安全なところ探し」という、ぼっち的素質を子供のときから見事にかねそなえ、しまいには「人間嫌い」になっていく中島少年なのであった。
もうこの時点で、涙なしには読めないのよ。
勉強はできたため、東大に入るも、入ったはいいものの、会社員にもなりたくない。働きたくない。何もしたいことがないので、モラトリアム無限地獄へと突入。何をやってもどうせ死んでしまう限りむなしい。でも何かをして生きていかなくちゃならない。そんで人並みに、人からリスペクトされたい。褒められたい。その他大勢に終わりたくない。という願望がふつふつと沸いてきて、「よし、じゃあ哲学をやろう! 哲学者ってオレみたいにしょっちゅう変なこと考えてても怒られなさそうだし、なんか世間的にもリスペクトされそうだし、いんじゃね?」という俗物根性で学部を哲学へと変えるも、そこでやっていたのは中島青年が日々悩んでいた「死んだあとはどうなるんだろう」「生きていたってなんの意味もないじゃないか」という悩みとは無縁の、デカルトやカントかどうたらとかつまんない授業ばかり。
しだいに大学に行かなくなる中島青年。「お願い大学へ行ってよ!」とドアの向こうから責める母親。ふとんにこもり、耳をふさぐ中島青年。まさにモラトリアムニート地獄絵図である。
さらに次の箇所が本書のなかで、最もドキッとするポイントというか、
ああ、哲学もダメだった、だったらオレは何をしたらいんだろう、と思う中島青年のたどりついた結論は「よし、作家になろう」ということであった。
負け犬だがプライドが保てる仕事はなんだろう。それはクリエイティブな仕事しかない。
「私はたしかに挫折した。私は考えに考えた。敗者なら敗者なりの美学を貫こう、せめて「美しい敗者」になろうと考えた。」(P45)
ある種の「人生を降りたい」と願ってやまない人たちはおそらく通ったことがあるであろう。美しい負け犬になろうという発想はまさにポールオースターのときにもあった、負けるが勝ち心理状態、負け犬憧れ、というやつである。
「勝者でも敗者でもない仕事は何であろうか? 他人と競争しなくてもよい仕事とは何であろうか。しかも、自分が矜持を保つことができる仕事とは何であろうか。そうだ、それは作家だ!」(p47)
「私は三文文士になりたいと思った。なぜなら、そこに私が表現するものは、客観的評価の手を滑りぬけるからである。客観的評価を受けなくとも、自己満足できるからである。自己催眠にかけられるからである。一冊の本もかけなくてもよい。「書こう」としている姿勢だけでよい」(P47)
もうここらへんの思考は、あまりに自分そのもので身の毛がよだった。
しかし中島青年。このとき二十すぎ。もちろん小説を書こうとはしないのである。「小説を書きたい」という夢を見ていれば満足なのであった。そうすると時間はずるずると過ぎていく。やりたくないことの言い訳のために夢を見る状態。一向に、外に出る気はしない・・・。さぁどうなるか、ということで大学紛争が起きる。
大学に行かなくてもいいとなり、中島青年、一筋の光明を見出す。「オレを苦しめてた世間の価値観が、今崩壊しようとしてる・・・これはチャンスだ」と、好きなことしようと思い立ち、勉強をしはじめる中島青年。一回、やめた法学部にまた再チャレンジとしたりと、ここから快進撃がはじまる!、のかと思ったら、「私はすぐに法学の勉強をやめた」といって、またやめたり、相変わらずグダグダなのである。
このグダグダは結局、「社会に出たくない」というモラトリアム根性から出た大学に残っていたいがための時間稼ぎともいえよう。これは大学を二回中退したボクも非常に、痛いほどわかるのだ。そんでもって中島青年。モラトリアムの権化として、12年間、大学のなかをうろちょろするのである。すごい。そのとき、すでに30歳。
ウィーンに留学して、博士論文を書いたことで、現在の哲学者という地位にまでのぼりつめるが、今まで出した著作をよめばわかるが、相変わらず、人間嫌いは健在だ。ファンが嫌いとか、どうせ死んじゃうし何をやったって無意味とか。ネガティブなことばっかり言ってる。もうステキ。
荒涼たる野辺をさすらうかのような憂悶の暗い20代の青春、そういう非フレッシュな青春を送ってきたボクには身にしみる自伝。いやほんとゾッとするほど自分のようなモラトリアムニートには恐怖の一冊、心をうつしたかのようなすごい自伝なんですぞ。