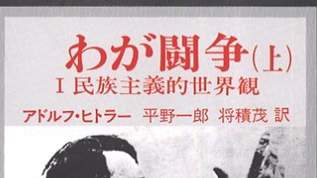【20歳の群像】第3回 三島由紀夫

本コラムの作者ドリーさんは、村上春樹氏の「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」Amazonレビューにおいて、日本記録である23000票以上の「参考になった」を集め、大きな話題になりました。
この連載「20歳の群像」では、過去の偉人が20歳の頃に何をしていたのか?
ドリーさんならではの視点と語り口で迫ります!(いまトピ編集部)


ついに三島由紀夫だ。ボクはそれを手にとった。恐る恐る。三島の自伝的小説、仮面の告白である。
「ついに」というのには理由がある。というのも仮面の告白執筆当時、三島由紀夫24歳。今これを書いてるボク今、24歳。同じ24歳もの同士、モノを書く身として、もう刃を交えざるをえないだろう、と思ったからなのだ。
たとえ昔の偉人であれ、同年齢、「君はどの程度のものをもってるのかな?」というのは絶対に避けられない事態だし、どちらが強いか、弱いか、というのは、読んだだけでわかってしまう。三島の思考、感性、ボキャブラリー、文章表現、問題意識、どれをとっても、ためされるのである。同じリングの上にたっている。お互いにハンデはない。同じ年月を生きてきたんだから、言い訳もできない。これは怖いぞ。
24歳という同じ階級にたってあらためて感じる向こうのでかさ。あのとき負わされた古傷の痛み。というのも三島には一度、こてんぱんにやられてるわけである。しかも16歳の三島に。

処女作「花ざかりの森」における、三島の「強さ」は、それはもう、16歳にもかかわらず、なんていうか場数を踏んできた「老師範」みたいだった。
「この土地へきてからというのも、わたしの気持ちには隠遁ともなづけたいような、そんな、ふしぎに老いづいた心がほのみえてきた」に始まり、「没落にともなう清純な放心、それはあらゆるものをうけいれ、あらゆるものに染まらない」とか、「ああそれが滔々とした大川にならないでなにになろう、綾織るもののように、神の祝唄のように」みたいな、16歳のくせに、84歳のジジイみたいな、こういう恐ろしく老練なパンチを放ってくるのである。
正直、震えた。リング上がってものの一分で、セコンドにタオル投げてくれって必死に目配せしてた。これは勝負するとかそんな次元じゃねぇって。それ以来、ボクの中で三島は「いないこと」になっていたのだが、ここへきて24歳という節目もあり、もう一度、リベンジしてしてやろうと思ったわけなのである。
三島は何を考え、24歳のときに何に悩んでいたのか・・・ちょうど企画にものれてるし、これはリベンジしない手はないと。
そして仮面の告白を読んでわかったこと。
24歳の三島は「ホモで悩んでいた」
ホモかー、と思った。
しかもただのホモじゃない。ちょっと複雑な、こみいってるホモだ。
「ホモじゃダメだ・・・ホモじゃダメだ・・・」とずーっと思ってるホモなのである。 仮面の告白ってのは、そんなホモな自分をありのままに述懐したっていう内容の本で・・・。
もっとざっくり言うと、三島の美意識というか、「あれも好きこれも好き」みたいな「おれはこんなところにグッとくる」っていう個人的フェティシズムを、あますことなくずーっと語ってるっていう、本なんである。
たとえば幼少期にジャンヌダルクの絵見て、ゾクゾクっとしたんだけど、女だと知って萎えちゃった、みたいな話から始まり、働くおっさんのあの働いてる姿、最高だな・・・とか、しまいには、いわゆるサド的な・・・少年のカラダに矢が刺さってるのを見ては「あぁ・・・」みたいな。さらには自分が鉄砲で撃たれて死んでるところを想像して「ああーー!!」みたいな。
まぁそういう三島の好色めぐりみたいな感じの内容で、それだけでもけっこう「キツイ」んだけど、さらにそのキツさに輪をかけるように、その語り口が、もうものの見事に「三島的」というか、
「ユイスマンは小説「彼方」のなかで、『やがて極めて巧緻な残虐さと微妙な罪悪に一転すべき性質のものなりし」ジル・ド・レエの神秘主義的衝動は、シャルル七世の……」
「私が幼時から人生に対して抱いていた観念は、アウグスティヌス風な予定説の線を……」
シャルル七世? ユイスマン・・・・?アウグスティぬす? いやもうこんな文章がいっぱいで、ほんとツライ・・・・のだ・・・。
たとえば三島が子供のときに、同級生の男の子を好きになっちゃった、みたいなエピソードなんか「好きになっちゃったー」って一言で書けばいいのに、三島は
「これが恋であろうか? 一見純粋な形を保ち、その後幾度となく繰り返されたこの種の恋にも、それ独特の堕落や頽廃がそなわっていた。それは世にある愛の堕落よりももっと邪悪な堕落であり、退廃した純潔は、世のあらゆる退廃のうちでも、いちばん悪質の頽廃だ」(p68)
こういう、なんかもういちいち「豪華絢爛」みたいな文章を書くのである。ムカつくのである。
そして読んでいると、ある致命的なことにぶつかったのである。オレは三島由紀夫のゴージャスな文体が嫌いなのだ、と。
いや嫌いって終わらせると話にならないので、まぁ仕方なく、読んでいくんだけど、結果的に言うと、三島は
「オレはホモだ・・・でもホモなんかおかしい。異常だ。男でありたい」っていう「男」への渇望が沸いてきて、そのこらへんの葛藤で右往左往して、「よし、がんばって女の子を好きなろう」つって友達の妹の園子って女の子と知り合って「よーし、この子を好きになるぞ、うん。可愛い」って自己暗示みたいに自分を奮い立たせて、向こうの女の子も運よく「三島さん、好き」みたいな感じできてくれて、うまいぐあいに付き合えて、デートとかしたときに園子が「三島さん!」みたいな、三島も「園子・・・」みたいな感じでガシッて抱き合ったりすんだけど、ところが三島「あれ、全然チ○コたたへん。全然ピクリともせーへん、あれ、これやばい、やばいこれ、フツーたつよな、フツーここでたたんとおかしいよな、あ、ダメだこれ、オレやっぱりホモかもしれんわ」みたいな感じになって、結局、女の子が「結婚して」って言ってきても、怖くなって振っちゃって、しばらくしたのち、「やっぱりあの子が忘れられない。もしかしたら今なら・・・今ならいけるかもしれない」って運よく再開したその子と、今度はダンスホールで踊ってみようとなって「三島さん」「園子・・・」ってまたいい感じになるんだけど、女の子のうしろにいた何人かの不良の若者に、三島、突然、目が釘付けになって「やばい、あそこにいる男の子たちめっちゃ可愛い、もうダメだわこれ、ホモじゃないようなフリしてきたけど、やっぱり完全にホモだわこれ」
ってなる。まぁ、そういう話。
24歳の三島は、「男」か「ホモ」かで葛藤していたのだった。
・・・・もうなんか勝負とかそんな気負いもなくなるぐらい、三島は個人的フェティシズムと格闘していたのである。
・・・20代の悩める若者には何の参考にもならない話で、ほんとうに今回は、ごめん。