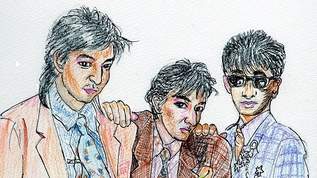小栗旬も心配な大河ドラマ後の仕事…『鎌倉殿の13人』和田義盛役の横田栄司が降板した舞台『欲望という名の電車』は多くの俳優が憧れた名作だった!
筆者は文学座公演『欲望という名の電車』(10月29日~11月6日紀伊國屋サザンシアター)の11月1日の夜の回を観に行った。
文学座『欲望という名の電車』の東京公演は2日間(10月29日と11月1日)のみ夜割で、通常料金6200円が4500円になる。
他にも夫婦割(2人で11000円)や25歳以下のユースチケット3800円、中高生が2500円だった。
だが、残念ながらチケットは11月6日分まですでに売り切れている。
筆者もやっと残り数席で後部座席を入手できた。
東京公演が終わると11月9日から岐阜県可児市、11月12日から兵庫県尼崎市での巡業があるので、近場であれば観る機会もあるだろう。
一般料金は6200円よりもっと安くなるらしいので、是非観に行って欲しい。
その価値はある内容だ。
主な登場人物は
ブランチ・デュボア(山本育子)
元高校教師。英語を教えていた。アメリカ南部の旧家の大農園の令嬢
スタンリー・コワルスキー(鍛治直人)
工場部品のセールスマン。ポーランド系移民二世。第二次大戦イタリア戦線の帰還兵。
ステラ・コワルスキー(渋谷はるか)
ブランチの妹。10年前に故郷を離れて、スタンリーと結婚。
ハロルド・ミッチェル(ミッチ) (助川嘉隆)
近所に住むスタンリーの友人。同じ戦線で戦った仲間でもある。病気の母親を抱える。
筆者は、一応あらすじは知っているつもりだったので、ヘビーな内容の為観るのが正直怖かった。
実際に観てみると、確かに悲劇的な内容だが、戯曲の構成はしっかりしていて、面白かった。
正直、筆者は映像の方が専門なので、舞台専門の俳優に詳しくない。
今回の文学座の出演者は、医者役で最後にだけ登場する小林勝也(1943年3月25日生れ)が『ちむどんどん』に出演していたので、唯一知っている俳優だ。
だが、かえってそのお陰で純粋に芝居の内容が入ってきたので良かった。
決め台詞が冒頭・前半・ラストと3箇所ある。
これは演出だと思うが、主人公のブランチがアルコール依存症の幻覚や幻聴を発症する様子が分かりやすい。
今でも何度も上演される理由として、ブランチのような病は精神医学の世界では比較的古くから研究されていたが、副主人公のスタンリーは明らかに戦争PTSDだ。
そのような人物は第一次世界大戦の帰還兵に関してはヘミングウェイの文学『日はまた昇る』等を読むと顕著に表現されている。(それ以前もおそらくいるだろう)
にもかかわらず、本格的にアメリカで研究が進んだのは、アメリカが歴史的敗戦をしたベトナム戦争(1955~1975)以降だと言われている。
『欲望という名の電車』は第二次大戦後の数年経ったニューオリンズの下町を描いている。
戦場から帰還した元兵士が抱える戦争PTSDはウクライナ戦争の今、決して遠い話題ではない。
当時としては、非常に先駆的な歴史的名作だったことがよく分かる。
では、何故この戯曲が初演当時画期的だったのか?
詳しくみてみよう。
文学座『欲望という名の電車』の東京公演は2日間(10月29日と11月1日)のみ夜割で、通常料金6200円が4500円になる。
他にも夫婦割(2人で11000円)や25歳以下のユースチケット3800円、中高生が2500円だった。
だが、残念ながらチケットは11月6日分まですでに売り切れている。
筆者もやっと残り数席で後部座席を入手できた。
東京公演が終わると11月9日から岐阜県可児市、11月12日から兵庫県尼崎市での巡業があるので、近場であれば観る機会もあるだろう。
一般料金は6200円よりもっと安くなるらしいので、是非観に行って欲しい。
その価値はある内容だ。
あらすじ
かつてはアメリカ南部の大農園で育ち、上流階級の娘であったブランチ・デュボア。
未亡人となった彼女は「欲望」という名の電車に乗り、「墓場」という名の電車に乗り換え、「天国」という名の駅に下車。
ブランチが降り立ったのは、今まで住んでいた街とは遠くかけ離れたアメリカ南部のニューオーリンズのフレンチクォーター。
この地に住む、妹のステラとその夫・スタンリーが住む貧しいアパートにたどり着き、3人の共同生活が始まる。
豪華絢爛な暮らしをしてきたブランチにとって、多民族が交差し合うニューオーリンズでの生活は衝撃的であった。
スタンリーは派手に振る舞うブランチに苛立ちを感じ、二人は反発しあう。
そんな中、スタンリーの友人のミッチと出会ったブランチは、自身の新たな希望を見いだすが…。
自身の過去に執着し続けるブランチ。
彼女とは対照的に現実を受け入れ、逞しく生きるステラ。
そしてスタンリー。
そして3人を取り巻く街の力強さ。全てのエネルギーがスパークし合う先に見える情景とは。
かつてはアメリカ南部の大農園で育ち、上流階級の娘であったブランチ・デュボア。
未亡人となった彼女は「欲望」という名の電車に乗り、「墓場」という名の電車に乗り換え、「天国」という名の駅に下車。
ブランチが降り立ったのは、今まで住んでいた街とは遠くかけ離れたアメリカ南部のニューオーリンズのフレンチクォーター。
この地に住む、妹のステラとその夫・スタンリーが住む貧しいアパートにたどり着き、3人の共同生活が始まる。
豪華絢爛な暮らしをしてきたブランチにとって、多民族が交差し合うニューオーリンズでの生活は衝撃的であった。
スタンリーは派手に振る舞うブランチに苛立ちを感じ、二人は反発しあう。
そんな中、スタンリーの友人のミッチと出会ったブランチは、自身の新たな希望を見いだすが…。
自身の過去に執着し続けるブランチ。
彼女とは対照的に現実を受け入れ、逞しく生きるステラ。
そしてスタンリー。
そして3人を取り巻く街の力強さ。全てのエネルギーがスパークし合う先に見える情景とは。
主な登場人物は
ブランチ・デュボア(山本育子)
元高校教師。英語を教えていた。アメリカ南部の旧家の大農園の令嬢
スタンリー・コワルスキー(鍛治直人)
工場部品のセールスマン。ポーランド系移民二世。第二次大戦イタリア戦線の帰還兵。
ステラ・コワルスキー(渋谷はるか)
ブランチの妹。10年前に故郷を離れて、スタンリーと結婚。
ハロルド・ミッチェル(ミッチ) (助川嘉隆)
近所に住むスタンリーの友人。同じ戦線で戦った仲間でもある。病気の母親を抱える。
筆者は、一応あらすじは知っているつもりだったので、ヘビーな内容の為観るのが正直怖かった。
実際に観てみると、確かに悲劇的な内容だが、戯曲の構成はしっかりしていて、面白かった。
正直、筆者は映像の方が専門なので、舞台専門の俳優に詳しくない。
今回の文学座の出演者は、医者役で最後にだけ登場する小林勝也(1943年3月25日生れ)が『ちむどんどん』に出演していたので、唯一知っている俳優だ。
だが、かえってそのお陰で純粋に芝居の内容が入ってきたので良かった。
決め台詞が冒頭・前半・ラストと3箇所ある。
これは演出だと思うが、主人公のブランチがアルコール依存症の幻覚や幻聴を発症する様子が分かりやすい。
今でも何度も上演される理由として、ブランチのような病は精神医学の世界では比較的古くから研究されていたが、副主人公のスタンリーは明らかに戦争PTSDだ。
そのような人物は第一次世界大戦の帰還兵に関してはヘミングウェイの文学『日はまた昇る』等を読むと顕著に表現されている。(それ以前もおそらくいるだろう)
にもかかわらず、本格的にアメリカで研究が進んだのは、アメリカが歴史的敗戦をしたベトナム戦争(1955~1975)以降だと言われている。
『欲望という名の電車』は第二次大戦後の数年経ったニューオリンズの下町を描いている。
戦場から帰還した元兵士が抱える戦争PTSDはウクライナ戦争の今、決して遠い話題ではない。
当時としては、非常に先駆的な歴史的名作だったことがよく分かる。
では、何故この戯曲が初演当時画期的だったのか?
詳しくみてみよう。