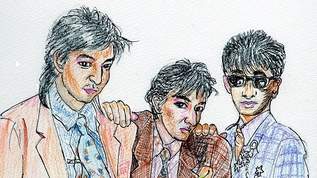吉永小百合が78歳にして初の祖母役!?『こんにちは、母さん』の監督・山田洋次が「日本映画をダメにした」と言われた経緯とは
『こんにちは、母さん』は山田洋次の90本目の作品だ。
そのフィルムグラフィーの半分以上が『男はつらいよ』50本である。
1969年から1995年までの48本と1本の特別編、甥の満男(吉岡秀隆)が主役の50作目がある。
『男はつらいよ』にマドンナ役で出演することは、日本を代表する女優であるというステイタスであった。
吉永小百合も第9作目『男はつらいよ 柴又慕情』(1972年8月公開)と
第13作目『男はつらいよ 寅次郎恋やつれ』(1974年8月公開)で高野歌子役で出演している。
吉永小百合の日活時代の先輩浅丘ルリ子はドサ回りの歌手リリーとして
第11作『男はつらいよ 寅次郎忘れな草』(1973年8月公開)
第15作『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』(1975年8月公開)
第25作『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』(1980年8月公開)
第48作『男はつらいよ 寅次郎紅の花』(1995年12月公開)
最多の4作品でマドンナを務めている。
『男はつらいよ』シリーズは前期は年2回制作されていたが、元々も結核で片肺を摘出している渥美清の体調が徐々に悪化していたので年に1本ペースに減った。
空いたスケジュールで、『学校』シリーズや単発の喜劇も数多く製作した。
記念すべき日本アカデミー賞の第1回作品賞を受賞したのが、山田洋次がピート・ハミルのコラムを映画化した
『幸福の黄色いハンカチ』(1977年10月1日公開)である。
渥美清の死後は、脚本のみで『釣りバカ日誌』に参加した。
藤沢周平3部作『たそがれ清兵衛』、『隠し剣 鬼の爪』(2004年10月30日公開)『武士の一分』(2006年12月1日公開)を発表した。
中島京子原作の『小さいおうち』(2014年1月25日公開)は、黒木華が第64回ベルリン国際映画祭最優秀女優賞(銀熊賞)を受賞した。

(『小さいおうち』 イラストby龍女)
山田洋次は、『三丁目の夕日』シリーズの山崎貴のような超特大ヒット作品の監督ではない。
確実にスマッシュヒットを出し、赤字を出さない。
打率の良いヒットメイカーである。
時代劇は人件費や衣装で予算がかかることを考えると、藤沢周平3部作で描いたように少人数での殺陣は予算の効率が良いはずである。
実は『男はつらいよ』シリーズの前半で寅次郎の夢という形で、公開当時流行っているジャンルの映画のパロディーをしているので、限られた枠の中で好きなことをしているという発想の豊かさなどが見られる。
そもそも『男はつらいよ』の主人公、車寅次郎は露天商を営むテキヤと呼ばれるアウトロ-である。
このシリーズは東映のヤクザもののパロディなのだ。
第1作目(1969年8月27日公開)での、午前様(笠智衆)の娘で幼なじみの冬子(光本幸子)とデートする時の目配せは、マキノ雅弘の演出を引用している。
津川雅彦の山田洋次批判は、かなり感情的な要素も見られる。
日活で「津川雅彦」としてデビュー後1958年に松竹へ移籍したが、1964年に退社している。
1969年にデヴィ夫人との不倫騒動もあって、仕事が激減した。
1973年に朝丘雪路との結婚後、誕生した一人娘の真由子が赤子の時に誘拐された事件でマスコミにあること無いこと書かれた。
長年確執があった兄の長門裕之が左翼だった事が積み重なった上で決定的な出来事があった。
東映の映画『プライド・運命の瞬間』(1998年5月23日公開)で津川雅彦は東京裁判における東条英機(1884~1948)を演じ、思想的に右傾化していった。
2004年には日本国憲法9条の改正に反対する『九条の会』は結成されたが、関連団体の「映画九条の会」の呼びかけ人の中に山田洋次も含まれている。
津川雅彦の山田洋次への対抗意識は、彼の経歴を観ると妙に納得するところがある。
筆者も津川雅彦は好きな俳優なので批判はしたくは無いが、山田洋次の件に関しては分が悪い。
山田洋次は喜劇作家でもある。
津川雅彦は侍がかっこ良く描かれていないことに不満を持っていた。
シナリオで人物を描くには登場人物のかっこ良さと悪さの二面性を描くことは当然だ。
ただしどちらを強調して描くかは作家性や表現の違いの問題で、それと日本映画が良くなるか悪くなるかは感情論で不毛な話なのである。
筆者はむしろ山田洋次は日本映画の良心であるとすら考えている。
撮影時間がサラリーマンの勤務時間並みに9時から17時まででちゃんと終わる。
良い作品は決して時間をかければ出来るとは言い切れない。
黒澤明が晩年作品数が少なくなったのは、撮影にこだわるあまりに予算を大幅に超えてしまったからだ。
スポンサーになってくれる企業を探すのに苦労したようだ。
ハリウッドで早撮りで有名なのは、クリント・イーストウッドとスティーヴン・スピルバーグである。
作品の質に撮影時間の長さは全く関係が無い。
気心の知れたスタッフと長年組んで職人技で制作していれば撮影時間を短縮して予算内で納品することは可能なことである。
山田洋次は、東日本大震災で延期した『東京家族』、志村けんのコロナ感染による死亡で主役交代があった『キネマの神様』以外はほぼ予定通りに、映画を順調に公開に踏み切ることが出来ている。
日本映画の将来を考える時に、山田洋次の制作の仕方はむしろ未来のやり方として再評価すべき素晴らしいモノではないだろうか?
※最新記事の公開は筆者のFacebookとTwitterにてお知らせします。
(「いいね!」か「フォロー」いただくと通知が届きます)
そのフィルムグラフィーの半分以上が『男はつらいよ』50本である。
1969年から1995年までの48本と1本の特別編、甥の満男(吉岡秀隆)が主役の50作目がある。
『男はつらいよ』にマドンナ役で出演することは、日本を代表する女優であるというステイタスであった。
吉永小百合も第9作目『男はつらいよ 柴又慕情』(1972年8月公開)と
第13作目『男はつらいよ 寅次郎恋やつれ』(1974年8月公開)で高野歌子役で出演している。
吉永小百合の日活時代の先輩浅丘ルリ子はドサ回りの歌手リリーとして
第11作『男はつらいよ 寅次郎忘れな草』(1973年8月公開)
第15作『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』(1975年8月公開)
第25作『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』(1980年8月公開)
第48作『男はつらいよ 寅次郎紅の花』(1995年12月公開)
最多の4作品でマドンナを務めている。
『男はつらいよ』シリーズは前期は年2回制作されていたが、元々も結核で片肺を摘出している渥美清の体調が徐々に悪化していたので年に1本ペースに減った。
空いたスケジュールで、『学校』シリーズや単発の喜劇も数多く製作した。
記念すべき日本アカデミー賞の第1回作品賞を受賞したのが、山田洋次がピート・ハミルのコラムを映画化した
『幸福の黄色いハンカチ』(1977年10月1日公開)である。
渥美清の死後は、脚本のみで『釣りバカ日誌』に参加した。
藤沢周平3部作『たそがれ清兵衛』、『隠し剣 鬼の爪』(2004年10月30日公開)『武士の一分』(2006年12月1日公開)を発表した。
中島京子原作の『小さいおうち』(2014年1月25日公開)は、黒木華が第64回ベルリン国際映画祭最優秀女優賞(銀熊賞)を受賞した。

(『小さいおうち』 イラストby龍女)
山田洋次は、『三丁目の夕日』シリーズの山崎貴のような超特大ヒット作品の監督ではない。
確実にスマッシュヒットを出し、赤字を出さない。
打率の良いヒットメイカーである。
時代劇は人件費や衣装で予算がかかることを考えると、藤沢周平3部作で描いたように少人数での殺陣は予算の効率が良いはずである。
実は『男はつらいよ』シリーズの前半で寅次郎の夢という形で、公開当時流行っているジャンルの映画のパロディーをしているので、限られた枠の中で好きなことをしているという発想の豊かさなどが見られる。
そもそも『男はつらいよ』の主人公、車寅次郎は露天商を営むテキヤと呼ばれるアウトロ-である。
このシリーズは東映のヤクザもののパロディなのだ。
第1作目(1969年8月27日公開)での、午前様(笠智衆)の娘で幼なじみの冬子(光本幸子)とデートする時の目配せは、マキノ雅弘の演出を引用している。
津川雅彦の山田洋次批判は、かなり感情的な要素も見られる。
日活で「津川雅彦」としてデビュー後1958年に松竹へ移籍したが、1964年に退社している。
1969年にデヴィ夫人との不倫騒動もあって、仕事が激減した。
1973年に朝丘雪路との結婚後、誕生した一人娘の真由子が赤子の時に誘拐された事件でマスコミにあること無いこと書かれた。
長年確執があった兄の長門裕之が左翼だった事が積み重なった上で決定的な出来事があった。
東映の映画『プライド・運命の瞬間』(1998年5月23日公開)で津川雅彦は東京裁判における東条英機(1884~1948)を演じ、思想的に右傾化していった。
2004年には日本国憲法9条の改正に反対する『九条の会』は結成されたが、関連団体の「映画九条の会」の呼びかけ人の中に山田洋次も含まれている。
津川雅彦の山田洋次への対抗意識は、彼の経歴を観ると妙に納得するところがある。
筆者も津川雅彦は好きな俳優なので批判はしたくは無いが、山田洋次の件に関しては分が悪い。
山田洋次は喜劇作家でもある。
津川雅彦は侍がかっこ良く描かれていないことに不満を持っていた。
シナリオで人物を描くには登場人物のかっこ良さと悪さの二面性を描くことは当然だ。
ただしどちらを強調して描くかは作家性や表現の違いの問題で、それと日本映画が良くなるか悪くなるかは感情論で不毛な話なのである。
筆者はむしろ山田洋次は日本映画の良心であるとすら考えている。
撮影時間がサラリーマンの勤務時間並みに9時から17時まででちゃんと終わる。
良い作品は決して時間をかければ出来るとは言い切れない。
黒澤明が晩年作品数が少なくなったのは、撮影にこだわるあまりに予算を大幅に超えてしまったからだ。
スポンサーになってくれる企業を探すのに苦労したようだ。
ハリウッドで早撮りで有名なのは、クリント・イーストウッドとスティーヴン・スピルバーグである。
作品の質に撮影時間の長さは全く関係が無い。
気心の知れたスタッフと長年組んで職人技で制作していれば撮影時間を短縮して予算内で納品することは可能なことである。
山田洋次は、東日本大震災で延期した『東京家族』、志村けんのコロナ感染による死亡で主役交代があった『キネマの神様』以外はほぼ予定通りに、映画を順調に公開に踏み切ることが出来ている。
日本映画の将来を考える時に、山田洋次の制作の仕方はむしろ未来のやり方として再評価すべき素晴らしいモノではないだろうか?
※最新記事の公開は筆者のFacebookとTwitterにてお知らせします。
(「いいね!」か「フォロー」いただくと通知が届きます)