「知らない女が毎日家にやってくる」親の認知症をめぐる現在進行形ドラマ『全員悪人』

「認知症」。もしも親が認知症になったら。しかも「義理の親」が認知症になったら。あなたはどこまで親身に介護できるでしょう。
おススメの新刊を紹介する、この連載。
第55冊目は、誰の身にも起こりえる「家族の認知症」をテーマにした実話ベースのドラマ『全員悪人』です。

■あの人は認知症。でも私は違う
「私を老人だと思って馬鹿にしたらいけないですよ」
村井理子(むらい・りこ)さんの義母は、そう言いました。
いつかは向き合わねばならない「家族の認知症」問題。実の親が、義理の親が、夫が、妻が、そして「自分」が、齢を重ねるとともに少しずつ「いま」を正しく把握できなくなってゆく。現実と夢想郷の境界があいまいになり、ファンタジックな存在になってゆく。
けれども自分の認知が歪みはじめている事実は決して認めない。「あの人は認知症かもしれない。けれども、私は違うのだ」と。いまそんな家族の介護に追われている人も、また多いのではないでしょうか。
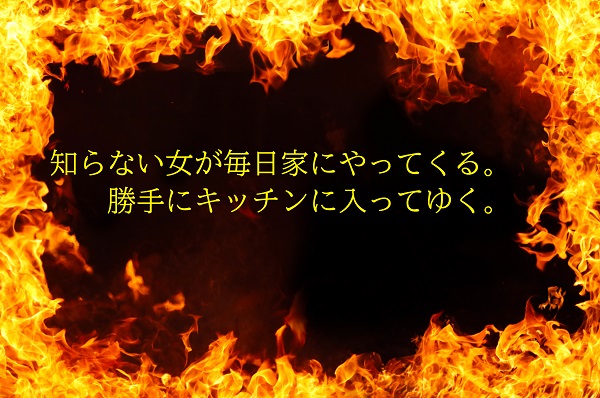
■夫がいつの間にか、ロボットと入れ替わっている
翻訳家・エッセイストとして知られる村井理子さん。村井さんは三年前、別居している義理の両親に変化が起きていると気がつきます。感情を自分でコントロールできず、いったい何に怒っているのか周囲は理解できない。特にコンディションの変化が顕著に表れたのが、義母でした。
財布の中のお金がなくなる。
知らない女が家にやってきて勝手にキッチンを漁る。
家族がこの女と結託し、家を乗っ取ろうとしている。
夫とこの女がデキている。
夫はいつの間にか、ロボットと入れ替わっている。
そうやって不満を爆発させ、村井さんが執筆中にもかかわらず、彼女はたびたび電話をかけてきます。
ときには、お金を盗んだ犯人だと疑って。
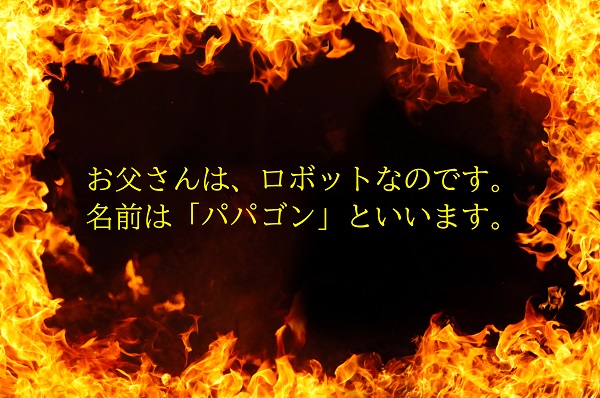
■誇り高く生きてきた私を侮辱する「全員悪人」
義母が発する言葉は、単なる不条理ワードではありません。むしろその怒りは、ほぼ理路整然としているのです。そしてロジカルに語る現状への不満は、六十年以上も夫に尽くし、子どもたちを立派に世に送り出し、華道の講師として多くの生徒を育ててきた誇りに裏打ちされたもの。まっとうに生きてきた一人の大人の女性として、凛とした姿勢が言葉の一つ一つに貫かれていました。
だから、若い女性たちから「お薬、ちゃんと飲みましょうね~」なんて、まるで赤ん坊のように扱われる筋合いはない。
自分は、どこも悪くはない。
薬など飲んでたまるか。
デイなんとかへ通うのは、あくまで認知症になった夫の付き添いなのだ。
なぜ私が童謡など歌わなければならないのか。
この私に向かって、ケアだのステイだの、偉そうに英語で名乗るな――と。
ただ、少々事実と違っていたことがあったんです。
それは……ケアする女性には、もうすぐ90歳を迎えんとする夫と浮気しようなんてマニアックな趣味はもちろんなく、そんな夫にそっくりなロボットをつくれるほどには、令和の科学は進歩していない点でした。
もう誰も信じられない。自分以外は「全員悪人」。そんなアウトレイジたちに囲まれ銃口を突きつけられるような日々を送る義母は、ロボットではない本物の夫が入院する病院まで、一人で出かけてゆきます。もちろん、病院がどこにあるのか、彼女は知りません。果たして、その後は――。
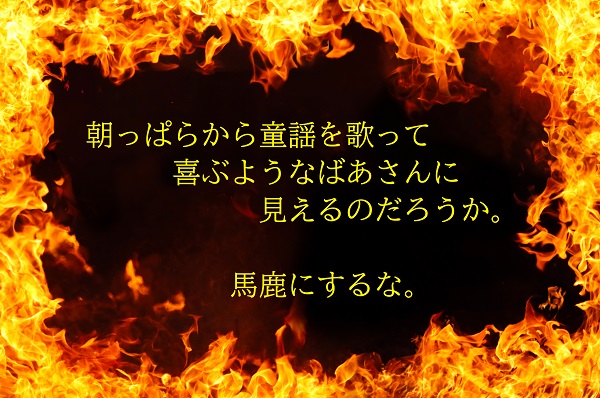
■認知症患者から見た世界は、どう映っているのか
村井さんは、そんな義母の現在の姿を本にしました。それが、ほとんどノンフィクションと言える新刊『全員悪人』(CCCメディアハウス)。
親の認知症や介護に関するの書籍は、すでにあまた発売されています。しかしこの新刊『全員悪人』は旧来の認知症関連書籍とは大きく異なります。なんと、義母の目線、つまり認知症当事者の視点で進行してゆくのです。
村井さんは義母に敬意を払い、発した言葉を丹念に記録。そこからドラマを構成してゆきます。認知症の当事者を主役に置くと、よかれと思ってやっていた行いが「違っていたのではないか」と気がつかされる。少女にやさしく諭すような話し方が、実は尊厳を傷つけていたかもしれない。「旦那様、素敵な方ですね~」と褒めた言葉が、嫉妬の炎をたぎらせるきっかけとなっていたかもしれない。よく「老いると赤ちゃんに戻る」と言われていますが、そう見えるだけだったのかも。芯にあるのは、いつまでもパートナーを愛し続ける、一人の成人なのですから。
村井さんはそうやって義母目線で物語を展開させながら、認知症になった家族とのつきあい方を読者に伝えます。この場面ではデイサービスの人に頼るのだ、ここで地域包括支援センターと連絡を取るのだ、など。ストレートにではなく、読者にサインを目配せするかのように。
特に義母が多額の水道詐欺に遭う「冷蔵庫に貼ってある水道修理マグネット事件」の項は有益な示唆に富んでいます。ただ、決して家族の誰をも責めない。悪いのはあくまで老人をターゲットにした詐欺師。そこに認知症になった本人、ガードできなかった家族への配慮を感じます。そしてやさしいからこそ、むしろ事件の痛ましさ、現代の病理が伝わってくるのです。
それにしても、義母がガチで憑依したかのような文章の見事さ。村井さんはトーマス・トウェイツの世界的ベストセラー『ゼロからトースターを作ってみた結果』(新潮社)など数々の話題の洋書を翻訳してきました。翻訳とは、海外の言葉を訳すだけではない。辻褄が合わない言葉から、その人の真の叫びを抽出する作業も翻訳なのですね。これがプロの仕事なのだと、うなります。
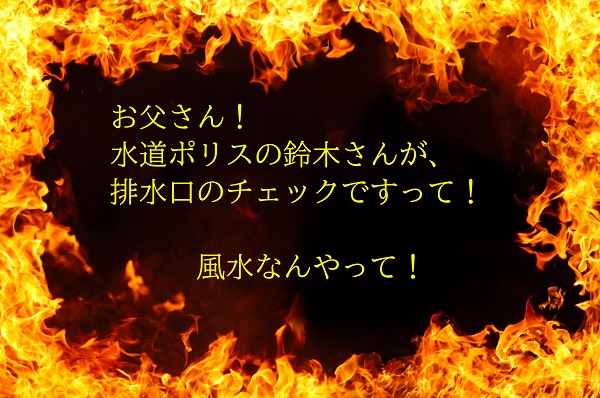
■プライドがあるから生きてゆける。でも……
この本を読んでいて苛酷だと感じるのが「誇り高く生きる」難しさです。
誇り高く生きる、それはとても大切なこと。しかし誇りの高さが実際の能力を越えたとき、人はとても扱いにくい存在になってしまう。だって誇りの高さ、プライドの高さほど、他人にとって「知らんがな」なものはないわけですから。
さらに誇り高さゆえ、自分は周囲からプライドをズタズタにされた被害者だと考えてしまい、疑心暗鬼に陥る。認知症とは、言葉とは裏腹に「認知できなくなる症状」。生きるとは、かくも難しい。
認知症が防ぎきれないものであるのならば、もしも自分がそうなったときに、潮時を認める覚悟をいまからしておいたほうがいいのでしょう。常日頃から自分と向き合い、「いつのまにかプライドが肥大化していないか?」「自己肯定が本来の能力を超えていないか?」を点検し続ける。自分がどう見られているか、ではなく「どうとも見られても思われてもいない」自覚をしっかり持つ。これってきっと訓練なんです。承認欲求を野放しにしていると、人はあまり幸せになれない気がします。
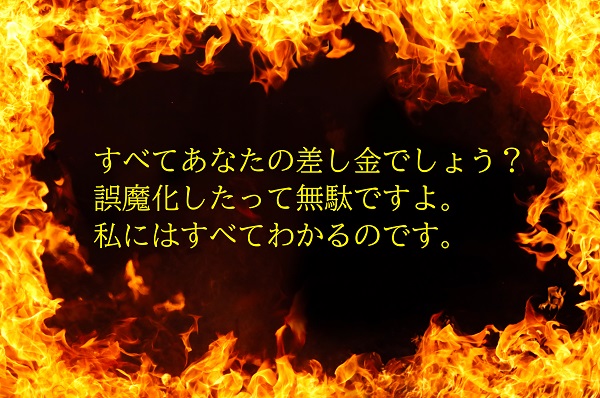
■家族の不幸をも書き残すプロ意識のすごさ
さて、村井さんは2019年に、疎遠だった兄の突然の死を経験しました。藪から棒に遺体の引き取り人となった記録を書籍『兄の終い』(CCCメディアハウス)に綴っています。……てことは、この2冊の本に書かれた騒動は、同じ時期に起きたんですよね。思わず息を呑みました
仕事にも支障をきたしたでしょう。自分だったら心、折れます。しかも新型コロナウイルス禍の渦中。それなのに身内の遺体の引き取りかたや親の認知症対策など、さまざまなノウハウをちゃんと読み物として書き残し、継ぎ手となる読者へ伝える。親族であっても記者の視点は忘れず、必要以上にエモくならず冷静に綴る。その姿勢に、鋼鉄のごとき物書きの矜持を感じずにはいられません。
文章を書くって、つまり「覚悟」なのだと思い知らされました。

全員悪人
村井理子 著
定価1540円(本体1400円)
認知症患者の不安や苦しさを「当事者」の目線で描くーー。
『兄の終い』で不仲の兄との別れを書いたエッセイストによる、新たな家族のドラマ。
「どちらさま? 誰かに似ているようですけれど」
私には居場所がない。
知らない女に家に入り込まれ、今までずっと大切に使い、きれいに磨き上げてきたキッチンを牛耳られている。
少し前まで、家事は完璧にこなしてきた。
なんだってできました。
ずっとずっと、お父さんのために、息子のために、なにからなにまで完璧に、私は家のなかを守ってきました。
あなたはいつも、お母さんって本当にすごいですね、完璧な仕事ですよと言ってくれた。
あなたに一度聞いてみたことがある。
なんなの、毎日代わる代わる家にやってくる例の女たちは?
そしたらあなたは、「お母さん、あの人たちは、お父さんとお母さんの生活を支援してくださっている人たちなんです。介護のプロなんですよ」って言ったのだけど、こちらは家事のプロですから。
――私は主婦を、もう六十年も立派に勤めてきたのです。
家族が認知症になった。
対話から見えた、当事者の恐れと苦しみ。
老いるとは、想像していたよりもずっと複雑でやるせなく、絶望的な状況だ。
そんななかで、込み入った感情を抱くことなく必要なものごとを手配し、ドライに手続きを重ねていくことが出来るのは私なのだろう。
これは家族だからというよりも、人生の先達に対する敬意に近い感情だと考えている。
(『あとがき』より)
家族が認知症になった。
悪気はない。
それでも周囲に迷惑をかけてしまう。
家族以上に戸惑い、苦悩しているのは本人なのではないか。
いろんな事件が起こる認知症当事者と家族の日々。
http://books.cccmh.co.jp/list/detail/2519/
吉村智樹





