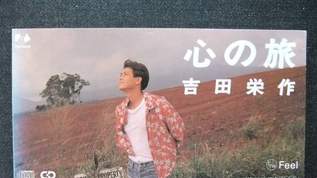アニメーターやプログラマーの時給はわずか○○円!バブル時代【フリーターの時給】まとめ
こんばんは、バブル時代研究家DJGBです。
一流ビジネス誌の『東洋経済』も特集を組むほどの「バブル時代ふりかえり」ブーム。
【「日本のバブル」とは、いったい何だったのか】 バブルが発生するための「2大原則」とは? : https://t.co/9m2t3JXoC4 #東洋経済オンライン pic.twitter.com/3qMJYGQd5a
— 東洋経済オンライン (@Toyokeizai) 2017年5月19日
何度も言うけどジュリアナ東京のオープンはバブル崩壊(91年3月)後の91年5月だから気を付けて。
ところで先日、「求人倍率がバブル期に肩を並べた」というニュースが。
景気「拡大」でも物価伸び悩み 求人倍率バブル期並み https://t.co/FdTebXAj4p
— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 2017年4月28日
厚生労働省が発表した3月の有効求人倍率(季節調整値)は1.45倍。バブル期の90年11月以来の高水準だそう。そういえば最近、近所の飲食店でも正社員や・アルバイト急募のビラを目にすることが増えた気がします。
そこで今日は、1冊の書籍からバブル時代のアルバイト事情をひも解きます。
■フリーター=既成概念を打ち破る新・自由人種
80年代中盤、特定の企業に社員として就職せず、フリーランス的に多くの企業から仕事を請け負ったり、短期の仕事やアルバイトで生計を立てたりする若者たちが急増します。ちょうど団塊ジュニア(70年代前半生まれ)世代たちが、夢を追って都会に集まり始めたころ。
好景気による建設ラッシュや、コンビニに代表されるチェーン店の発達が、そうした若者の雇用の受け皿となりました。
87年、リクルートのアルバイト求人雑誌『FromA(フロム・エー)』編集長 道下裕史(当時は道下勝男)は、こうした新しい働き方を“フリーター”と名付けます。

同年出版された書籍『フリーター』(リクルート フロム エー)には、冒頭にこんな一文が躍っています。以下引用。
1987年、既成概念を打ち破る新・自由人種=フリーターが誕生した!
敷かれたレールの上をそのまま走ることを拒否し、いつまでも夢をもちつづける。
たちはだかる困難からさらりとスマートに身をかわす。
そして何よりも自由を愛する。
世の中のワクにはまることなく夢を追い求めるフリーターこそ、社会を遊泳する究極の仕事人。
リクルートは夢を追う若者たちを、人手不足に悩む企業と結び付けることで急速に成長します。“フリーター”という言葉にも現在のようなネガティブなニュアンスは全くなく、道下の言葉を借りれば“究極の仕事人”を指していました。
●リクルート『フロム・エー』(87年ごろ)
同年、『フロム・エー』創刊5周年記念として制作された映画「フリーター」(主演・金山一彦、鷲尾いさ子)で描かれているのは、斬新なアイデアでひと儲けを目論む学生サークル。今の言葉でいえば“学生ベンチャー”です。

こうした仕掛けが功を奏し、“フリーター”という言葉は急速に普及。新語・流行語大賞こそ「DODA/デューダ(する)」(89年・学生援護会)に譲りましたが、“フリーター”も91年には『広辞苑』にも収録されました。
なおあえて付け加えれば、政界・財界を巻き込んだ“リクルート事件”が発覚するのは、88年6月のことです。
■バブル期の“フリーター”のフトコロ事情は?
87年の大卒初任給は148,200円(出典:厚生労働省 賃金構造基本統計調査)。1日8時間、21日働いたとして、単純計算で時給は約880円です。
ちなみに86年当時の東京の最低賃金は488円。タバコ「マイルドセブン」が1箱220円、ラーメン二郎の「ぶたダブル」は1杯250円、マクドナルドの「ビッグマック」はなんと1個420円でした。
では“フリーター”たちの生活は、いかほどだったのでしょうか。
前出の書籍『フリーター』には、当時の『フロム・エー』編集部が職種別の平均時給をまとめた「現代アルバイト事情」が収録されています。その中から、いくつか注目の職種と時給をピックアップします。
出典:『フリーター』(リクルート フロム・エー)。なおこの調査は『フロム・エー』昭和61年3月4日号~昭和62年2月10日号に掲載された求人情報から算出したもの。経済統計上、バブル経済のはじまりは86年(昭和61年)12月ですから、ほぼ“バブル前夜”の時給です。
現在でも定番のアルバイトとその時給はこんな感じ。
●ファーストフード加工・販売…630円
●書店員…587円
●ガードマン…822円
●塾講師…869円
●レジ…703円
●皿洗い…688円

地域によっては、今でもこのぐらいの相場のところもあるかもしれませんね。
バブル期と言えばリゾート。当時のリゾート地はフリーターたちで支えられていましたが、その時給は比較的低めです。
●ホテル業務スタッフ…575円
●スキー場業務…591円
●ツアーコンダクター…626円
●リゾート地スタッフ…446円

最後の「リゾート地スタッフ」はリスト中で最も低賃金ですが、要は軽井沢とかのペンションのお手伝いスタッフですかね?
リスト中には、他にもバブル感を醸す仕事が。
●イベント要員…754円
●キャンペーンガール…836円
●ショールームコンパニオン…656円

いっぽう、時給900円以上の職種は、この3つだけ。
●貿易事務アシスタント…979円
●仲居さん…1062円
●新聞のセールス…1111円
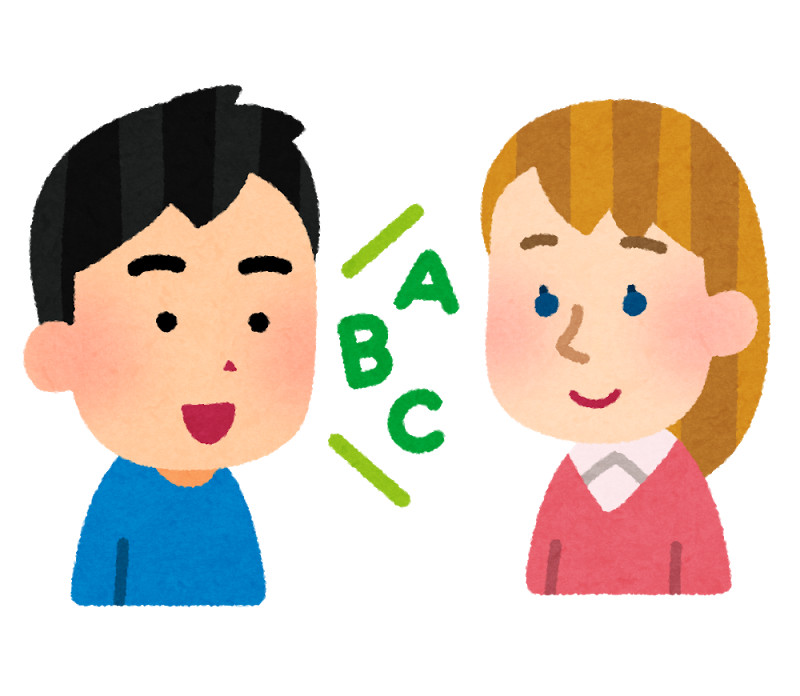
舶来ブランドが大量に輸入されたバブル期、英語のできる人材は今よりさらに貴重な存在。ところで新聞のセールスって、ノルマ制じゃないんですかね?
現代ではなくなりつつある仕事も…。
●DPE受付…601円
●レタリング…700円
●版下製作…727円

「ハンゲ…??」と思った平成生まれのヤング諸君、版下は「はんした」と読みます。雑誌やポスターの最終的な原稿を作るお仕事で、とうぜん印刷に回したあとは修正不可能、ミスは許されません。撮影済みのフィルムを現像してもらうために持ち込こむDPE店は、かつて街のあちこちに存在しましたが、現在ではずいぶん減りました。
●プログラマー…811円
●キーパンチャー…796円
●タイピスト…810円

最近は中高生のなりたい職業1位に挙げられることもあるプログラマーの時給は、キーパンチャー(コンピューターにデータ入力をする人)、タイピスト(タイプライターで書類を清書する人)とほぼ同じ。3つに共通するのは「キーボードを使って文字入力する」ということだけのような気が…。
●アニメーター…659円

現在でも過酷な労働環境がたびたび取り沙汰されるアニメーターの時給は、当時も低めです。日本アニメーター・演出協会が2015年に発表した調査によれば、年収200万円以下のアニメーターも27%(平均年収は332.8万円)いるそうですから、待遇はこの30年、あまり変わっていないのかもしれません。
■バブル前夜には、組織に縛られない生き方が注目される?
バブル時代、英語やコンピューターが使えることはまだまだ特別なスキルで、才覚とやる気のある若者は、特定の企業に就職しなくても、いやむしろ就職しないほうが、短時間で高収入を得られることもありました。
いつの時代も、組織に縛られない自由な生き方は魅力的です。ただし、多少のオカネがあれば、の話です。
バブル期、アルバイトのニーズは上昇の一途をたどります。
リクルート事件の逆風にもかかわらず、リクルートは毎週火曜日発売の『From A』に加え、89年、新たに毎週金曜日発売の『From A to Z』を創刊。当初関西版のCMソングとして制作された河内屋菊水丸による「カーキン音頭」も大ヒットしました。
この「カーキン音頭」のCD発売は、実はバブル崩壊後の91年4月3日。その後、景気は低迷し、”フリーター”という言葉が持つニュアンスも激変しました。『フロム・エー』もフリーペーパーやインターネットにとってかわられ、09年、休刊しています。
組織に縛られず、夢を追いながら、好きなことで生きてゆくことは、なかなか難しいものです。
「好きなことで、生きてゆく」
あれ、こんな言葉、最近どこかで聞きませんでしたっけ? またバブル来てるのかな。
(バブル時代研究家DJGB)