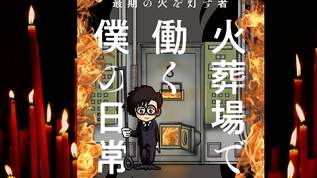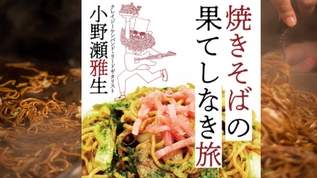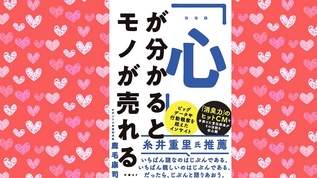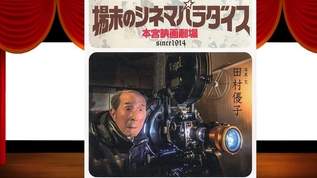ゴールデンウイーク穴場情報!きのこライターに訊く「京都きのこスポット」

▲きのこだらけ部屋にいるこの女性、いったい誰……
こんにちは。
関西ローカル番組を手がける放送作家の吉村智樹です。
こちらでは毎週、僕が住む京都から耳寄りな情報をお伝えしており、今回が35回目のお届けとなります。

さていよいよ今週から待望のゴールデンウイークに突入しますね。旅行や行楽のプランをたててワクワクされている方もきっと多いでしょう。
私が住む京都はというと、名だたる一大観光都市。ゴールデンウイークの時期は大げさではなく1メートル歩くのも困難なほどに、繁華街や観光スポットは人で埋め尽くされます。ドローンで撮影すればきっと、人間がエノキタケのようにぎっしりひしめいて映るでしょう。
というわけで今回は、それほど混まない場所で楽しめる京都の穴場レジャー情報をお教えしましょう。
それが「きのこ鑑賞」。
観光ガイドブックには載ってはいませんが、実は京都は「きのこを楽しめる街」でもあるのです。
■きのこLOVEな女性きのこライター登場!
ナビゲートしてくれるのは、この方。
京都在住の堀博美さん(46歳)。

▲きのこについての著書を多数上梓された”きのこライター”の堀博美さん
堀さんの職業は、ひたすらきのこについて書きまくる“きのこライター”。ベストセラー『ときめくきのこ図鑑』(山と溪谷社)や、カジュアルなきのこブームを巻き起こした『きのこる キノコLOVE111』(同)、最新著書『珍菌 まかふしぎなきのこたち』(光文社)など、きのこにまつわる著書をたくさんお持ち。

▲”きのこ女子”ブームを生みだした堀さんのきのこ本の数々
堀さんは、なんと沖縄で新種も発見したエキスパート。きのこの関連書は多くありますが、「ときめき」「LOVE」といった愛でる視点を積極的に採り入れたパイオニアなのです。

▲堀さんが借りている仕事部屋は、やっぱりきのこ でいっぱい

▲かわいいきのこグッズのコレクションもズラリ

▲「きのこ漫画」というジャンルがあることがわかる、きのこ関連コミックスの数々

▲冷蔵庫には手作りのきのこマグネットが

▲きのこをまつった「菌神社」(くさびらじんじゃ)のお札も
そんな堀さんが、きのこに関心をいだいたきっかけはなんだったのでしょう。
 堀
堀
「小学校6年生のクリスマスの日、父が書店で私に『*ブルーバックスから好きな本を10冊プレゼントするから選びなさい』と言い、なんとなく表紙に惹かれ、小林義雄さんの『菌類の世界』を手にしたんです。それまで特にきのこに興味があったわけではなく、小林義雄さんが菌類の分類学的研究の権威であることもまだ知りませんでした。そうして初めて触れたきのこの本が、とても面白かったんです」
註*「ブルーバックス」……講談社が刊行している、自然科学全般の話題を一般読者向けに解説している新書レーベル。

▲堀さんのきのこ歴は小学生時代からスタート。きっかけは『菌類の世界』
小学生には少々難しいと思えるブルーバックスを買い与えたお父様、えらい! 子供には子供向けの本を、ではないんですよね。
■ベニテングタケに出会ってきのこを熱愛
そんなふうに深奥なるきのこの世界への第一歩を踏み出した堀さんが、さらにのめりこむきっかけとなったのが大学時代。
 堀
堀
「京都教育大で美術を学んでいた頃、作品のモチーフを探すために大学の図書館で『日本のきのこ』という図鑑を観ていて、そこに載っていたベニテングタケの美しさに見とれてしまったんです。かさが赤くて柄が白く、『なんて素敵なデザインなんだろう』って」

▲堀さんが撮影したベニテングタケ 。自然がつくりあげた完璧なデザイン
ベニテングタケの神々しいまでの美しさに、たちまち菌じられた恋におちた堀さん。いてもたってもいられず、憧れのスターに会いに行ってしまいます。
 堀
堀
「どうしても現物が観たくなり、夜行バスに乗って、ベニテングタケが自生するという長野県の菅平まで行きました。現地に到着し、朝のうちに観に行ったら、ベニテングタケが白樺の樹の下に生えていたんですよ。本物を見て、さらに感動してしまいました。その日に泊まった『ペンションきのこ』でいただいた野生のきのこ鍋がこれまたおいしくて、『これはきのこにはめられた』と思いました(笑)」
この強烈なきのこ体験により一気に「きのこる」ライフへと突入した堀さん。在学中にベニテングタケの研究結果を記したミニコミ『*SOMA TIMES』(ソーマ・タイムス)を定期刊行し、きのこにまつわる文章を書き始めます。
註*「SOMA(ソーマ)」……古代インドの聖典『リグ・ヴェーダ』に記された聖植物のこと。「ソーマ」の正体はベニテングタケではないかと言われている。
つまり堀さんのライターとしてのスキルは、ベニテングタケへの愛によって育まれたのです。その集大成となったのが丸ごと一冊ベニテンタダケのことだけを貫いて書いた『ベニテングタケの話』(ヤマケイ新書)。
ちなみに「堀博美」は実はペンネーム。ベニテングタケが聖なるきのこと呼ばれていることから、「聖なる」→「ホーリー」→「堀」になったのだとか。
■毒きのこを食べてしまった経験も
ところでベニテングタケといえば、毒きのことしても知られています。調査をするうえで、危険な目に遭ったことはないのでしょうか?
 堀
堀
「実は……毒きのこであることは重々知ってはいたんですが、あまりに美しいので、我慢できずに食べてしまったことがあるんです。案の定すごい吐き気が襲ってきたんですが、なぜか『吐いちゃったらもったいない』と思ってしまって(笑)。そうするうちに、ぼんやりした気分になり、視界が白っぽくなっていって……危険でしたね。友達は2階から飛び降りようとして、必死で止めました。やっぱり、どんなに愛しているからって、食べちゃダメですね」
堀さん、実はこれまできのこの研究のさなかに何度も食中毒になっており、「きのこライター」はやはりたいへんな仕事なようです。
 堀
堀
「誤って、食用のオオイチョウタケにそっくりな毒きのこを食べてしまい、2日目から激しい吐き気と下痢に悩まされたこともあります。毒きのこのなかには食用きのこに激似なものもあるんですよ。病院へ行ってもお医者さんから『僕はどうしたらいいの?』と逆に尋ねられて困りました」
患者に訊かれても困りますよね。
 堀
堀
「日本にはおよそ240種類の毒きのこが発見されており、お医者さんが対症法を知らないものもあって、死に至る場合も。毒きのこの特徴ですか? 毒きのこってひとつひとつに特徴があり、反対に毒きのこならではのこれっていう特徴はないんですよ。見た目にとても地味な種類もあって、一種一種、憶えるしかない。野生のきのこは危険です。食用とされていても生食は危ないので気をつけてくださいね」
毒きのこならではの特徴はなく、一種一種憶えなければならない……いやぁ、「ライターは専門分野を持て」とよく耳にするけれど、「それは生半可な覚悟ではないよな……」と改めて思いましたね。
■『探偵!ナイトスクープ』に依頼したことも
このように身を挺して毒学しながら観察したきのこはこれまで1000種を超えるのだそう。なかでもとりわけ印象深いきのこは?
 堀
堀
「イカタケです。イカがさかさまに地面に刺さっているように見える白いきのこで、絶滅危惧種。幻のきのこと呼ばれているんです。私はイカタケが地面から生えてくる姿がどうしても見たくて見たくて、テレビの力を借りるよりほかなく、『探偵!ナイトスクープ』に応募しました。探偵の松村邦洋さんと一緒に4時間かけて観察しました」

▲堀さんが『探偵!ナイトスクープ』に依頼したことをきっかけに動画の撮影に成功したイカそっくりのイカタケ。きのこ研究の歴史上、たいへん貴重な資料となった
イカタケ……ああ、あの依頼者の方が堀さんだったのか! と、思いだされた方も多いのでは?
■きのこライターに訊く「京都きのこ鑑賞スポット」BEST3

では、日々きのこをリサーチし続ける堀さんに、京都で*きのこ鑑賞ができるスポットを三か所、お教えいただきました(以下、きのこの写真は堀さん自ら撮影したもの)。
*「きのこ鑑賞ができるスポット」……注意! 以下で紹介するきのこスポットは、あくまで鑑賞やスケッチ、撮影ができる場所。採集したり傷をつけることは許されてはいません。
まず一か所目は?
 堀
堀
「長岡京市の竹林です。長岡京市は観光竹林が多く、適度に手入れがされているので観察がしやすいです」
どんなきのこが観られますか?
 堀
堀
「初夏からキヌガサタケを観ることができます。基本的に竹林にしか生えないきのこで、長岡京市はキヌガサタケファンにとっても有名な場所なんです。食用に適し、レースの部分はおいしい。中華料理屋さんではメニューに載ることもあり、一本5000円で取引されるような高級食材です。ただ……味はいいのですが、とにかくにおいが強い。肉が腐ったような臭さ。ハエがたかることもあります。生で見るとその強烈なにおいにあてられるんですが、反面においのおかげでどこにあるかがわかるため、比較的見つけやすいですね」

▲ドレスをまとう貴婦人のように華麗な姿のキヌガサタケ。しかし匂いが強烈。言わば貴腐人
初夏のきのこですか。「きのこは秋」というイメージでしたが、実際はどうなのでしょう。
 堀
堀
「松茸の旬が秋なのでそういうイメージがありますが、たくさんの種類を観察するなら、いまから7月までのほうが楽しめますね。いま挙げた長岡京市ならアミガサタケは春からのきのこで、ゴールデンウイーク中も目撃できるかも。竹林だけではなく桜やイチョウの下に生えている場合が多いです。味もいいし、見た目にも愛らしいのでファンが多いですよ」

▲しわしわな見た目がインパクト大。うまみが豊富で、イタリアンや洋食の食材としても人気のアミガサタケ
では二カ所目は?
 堀
堀
「清水山です。清水山は、いろんな種類のきのこを見ることができ、観察が楽しいです。比較的容易に見つけられるのがチシオタケ。ピンクで愛らしいきのこですが、傷がつくと紅い液体がにじみ出てくることから“血潮”と名づけられています。毒々しい? 見た眼に反して毒きのこではないのですが、食べごたえはなさそうですね」

▲傷がつくと血のような液体が染み出るチシオタケ。かさが薄く、色がパープルで気品がある。言わばきのこ界のヴィジュアル系
では最後に三カ所目は?
 堀
堀
「京都御苑です。自然発生しているきのこを観察できる絶好のスポットですね。私が京都御苑のきのこで好きなのがツチグリ。幼菌のときは小さな玉のような形をしており、土の中にいます。この小さな玉を炊き込みご飯の具に使う地方もあるようです。成長するにしたがって地表に現れ、ヒトデのように外皮が開きます。乾燥すると閉じて、自ら転がっていって胞子をまくんです」

▲湿気を感知し、外皮を開いたり閉じたりするツチグリ
尾籠な表現ですが、上から見た姿が、お尻の穴みたいですね。
 堀
堀
「この穴から煙のように胞子を吹き出すんですよ。外皮で自分自身をつついて胞子を飛ばすこともあるんです」
それはもう本格的におならですね。そういえば、京都御苑では希少な発見もあったそうですね。
 堀
堀
「はい。ブンゴツボマツタケ(仮)です」
カッコ仮、ですか?
 堀
堀
「はい。京都御苑のきのこを観察する集会で見つけました。大分県にしか生えていないはずのきのこを京都で発見し、御苑の方に連絡を取りました。職員の方がカラーコーンを置いて近づけないようにしたり、なかなかものものしい雰囲気になりました。そののち博物館へ寄贈し、本当にブンゴツボマツタケなのかどうかを調査することになったんです。きのこを調べていると、そういう貴重な経験をすることがあるんです」

▲大分県にしか自生しないと言われていたはずのきのこを京都御苑で大発見。だから暫定的に「ブンゴツボマツタケ(仮)」
きのこLOVEな暮らしを送っていると、そういった学術的に重大なシーンに立ち会うこともあるのですね。そんな堀さんにとって、きのこの魅力とはなんでしょう。
 堀
堀
「うーん、ひとことでは言えないですね。かわいらしかったり美しかったり、毒があってミステリアスだったり、食品としてもおいしい。木と共存関係を結んでお互いに栄養や水をやり取りして生きていく姿、落ち葉や動物の死骸を分解して自然に還してあげる様子、どれも愛おしい。そういう多面的なところが魅力なのでしょうね」
多面的な魅力を秘めた神々しききのこは、言わば自生した金閣寺。
ゴールデンウイークのゆったりしたひとときに、京都のきのこを鑑賞し、香りを嗅いで、ワンデイ・トリップしてみませんか?
(吉村智樹)