元・火葬場職員のアーティストが見た壮絶な実態『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』
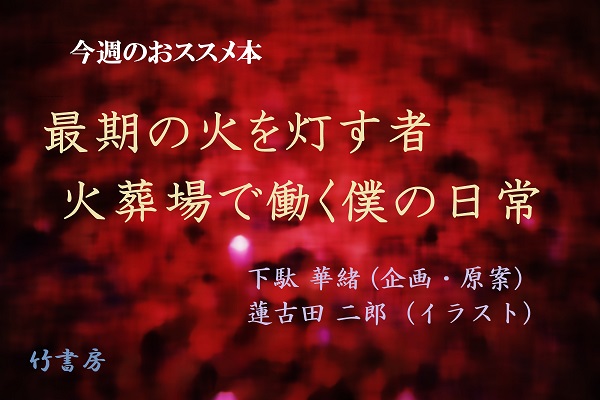
「新型コロナウイルス、いよいよ収束か!」
新型コロナウイルスの感染スピードが急速に落ち、新規感染者ゼロを記録する都道府県もあらわれはじめた昨今。再拡大の懸念はもちろんありますが、ピークが去った事実をいまは素直に喜び、噛みしめたいです。
そんな新型コロナウイルス禍によって大きく注目されたスポットがあります。それが「火葬場」。
火葬場での感染防止のノウハウが確立していなかった時期は、死亡から遺体の火葬までに10日以上も要したケースがありました。また、家族との「最後の対面」も許されなかったのです。
現在は少しずつナレッジが整いつつあり、遺族の立ち合いも認められるようになってきたのだそう。もちろんそのかげには、火葬場職員の方々のひたむきな努力がありました。「近しい人たちで送ってあげてほしい」という、職員さんたちの想いがあればこそ可能にしたのです。
誰しもが避けられぬ、死。火葬場は言わばこの世から天界へ飛ぶための搭乗口。そんな大切な場所なのに、私たちは、あまりにも火葬場の様子を知らない。
おススメの新刊を紹介するこの連載、第70冊目は、知られざる「火葬場職員」の世界を描いたコミックエッセイ『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』です。

■前職が「火葬場職員」。意外な経歴を持つアーティスト
アーティストには意外な職歴をもつ人がいます。たとえば氷室京介さん。氷室さんはミュージシャンになる以前は英会話教材のセールスマンとして高い成績をおさめていました。藤井フミヤさんは国鉄(現:JR九州)の職員。ヘルメットをかぶり、労働闘争に参加した経験もあるのだそう。YUKIさんはバスガイド。バスガイド時代の経験をもとにした「バスガール」という曲があります。
バンド「ぼくたちのいるところ。」のベーシストとしてメジャーデビューを果たした下駄華緒(げたはなお)さんの前職は、アーティストのなかではとびきり稀少です。なんと「火葬場職員」。火葬技士1級の免許を取得した、いわゆる「おくりびと」。およそ1万人の遺体を納棺や火葬した体験があるのです。
■「おくりびとミュージシャン」が経験した壮絶な現場
そんな異色の経歴をいだく下駄さんが新刊『最期の火をともす者 火葬場で働く僕の日常』(竹書房)をリリースしました。
この新刊は下駄さんが原案を担当し、漫画家の蓮古田二郎さんがコミックにした実体験エッセイ集。下駄さんは先ごろ40日に及ぶ過酷な「四国八十八箇所の歩き遍路」を達成しました。このようにアーティスになった現在もつねに生と死に向き合いながら活動しており、命への真摯な姿勢と慈悲に満ちた視点が一コマひとコマに映し出されています。それゆえ、読者をしみじみと深い感動へと導いてくれるのです。
■遺体が爆発! 猛烈なニオイ! 火葬場の裏側は凄絶だった
下駄さんが火葬場職員を志したのは「人生最後のしめくくりをしてあげられる、すばらしい仕事」だと感じたから。そうして、先人たちが不当に「差別された」時代もあるこの職業に高い意識を以って挑んだのです。

(c)hanao geta (c)jiro hasukoda
しかし現実は想像していたよりもずっとハード。火葬場職員はご遺体がきれいにお骨になるよう「焼け具合」をつねに観察しなければなりません。さらに猛火がさかる炉に専用の器具を挿しこみながら骨の位置を調整する必要があります。けれども、あぶられた遺体は血液を噴出させながらスルメイカのようにぐるっと反りかえり、なかにはまるで生き返ったかのごとく起き上がる場合もあるのです。そして頭をひねり、こちらに顔を向けるケースも……。
それだけではありません。心臓に埋められたペースメーカーが炉のなかで爆発し、肉片が自分の顔めがけて弾丸のように飛んできたり、開頭手術をして頭蓋骨があいたご遺体の脳が焼けて猛烈な臭気を放ったり、棺の底がずぶ濡れになるほどたっぷりと水分を吸った水死体がなかなか焼けなかったりなどなど、下駄さんは高熱と臭気にさいなまれながらご遺体と闘う日々を送ることに。ホッとできるのは、棺に納められたメロンが焼けていい香りを放つときくらい。

(c)hanao geta (c)jiro hasukoda
■火葬の火は最期のスポットライト
それにも増して下駄さんが胸を痛めたのが、自分の祖母と、自分よりもずっと若い少年を焼いた日でした。職員でありながらお骨上げの際に涙が止まらず、下駄さんは「むいていないのではないか」と苦悩します。
私は過去に二度、火葬場で骨上げの箸渡しを経験しました。一度目は実の弟、二度目は当時組んでいたバンドメンバーの女の子。一度目は、実の弟の骨を箸でつかむ極限の状況から気が遠くなり、涙が出ませんでした。二度目は、お骨を壺におさめる作業中に涙がせきを切り、その日は「このまま精神に異常をきたすのではないか」と思うほど泣きました。それは箸渡し(橋渡し)の深奥なる意味を知ったゆえの涙。メンバーだけではなく弟の骨を拾ったあの日の記憶も蘇り、悲しいけれども「なんて崇高な行為なのだ」と魂が震えたのです。
思えば、火葬場職員の方々が、お骨を美しい状態に補整してくださったからこそ、見送った人たちの気持ちが澄んだものでいられたのでしょう。
下駄さんは職場が職場だけに火葬場で理屈では説明がつかぬ怪異な体験を何度もします。でも、そのとき下駄さんは「怖くなかった」のだそう。火葬場へ運ばれてくる遺体は、その数だけドラマがある。そのすべてのドラマに畏敬の念を払うからこそ、きっと「怖くない」のです。
火葬の火は、ひたむきに生きてきた人をねぎらうために灯された、最後のスポットライトなのかもしれません。そして火葬場職員は人生のラストステージを後悔なきよう演出する尊いお仕事なのだと改めて気づかされました。

最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常
著者名:原案:下駄華緒/漫画:蓮古田二郎
定価:1,210円 (税込)
竹書房
“僕の仕事は亡くなった人をあの世に送ること――。”
YouTubeチャンネル「火葬場奇談」が話題!! これまでに1万人のご遺体を見送った男・下駄華緒の火葬場職員時代の壮絶体験を漫画化!!
* * * * * * * *
「火葬場職員は人生の締めくくりをしてあげられるすばらしい仕事」と熱い気持ちを抱き火葬場の門を叩いた下駄華緒。
晴れて火葬場職員になった下駄青年であったが、火葬場では日々壮絶な出来事が待ち受けていた――。
火葬炉の火の中で動き出すご遺体、火葬中に破裂したご遺体の骨片や肉片による怪我、ずっしり重く豆腐のような状態で棺に収められた水死したご遺体などなど――。
個性あふれる同僚職員たちと様々な業務を通し、一人前の火葬場職員になるまでの日々を描く――!!
http://www.takeshobo.co.jp/book_d/shohin/5119001
吉村智樹
https://twitter.com/tomokiy





